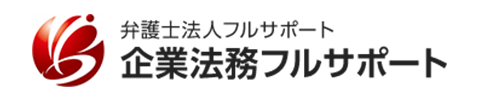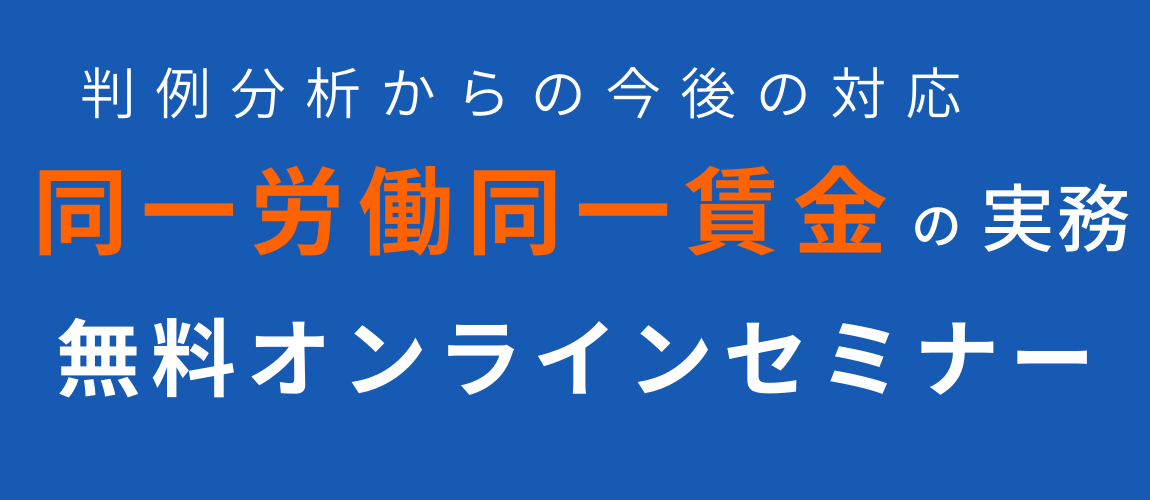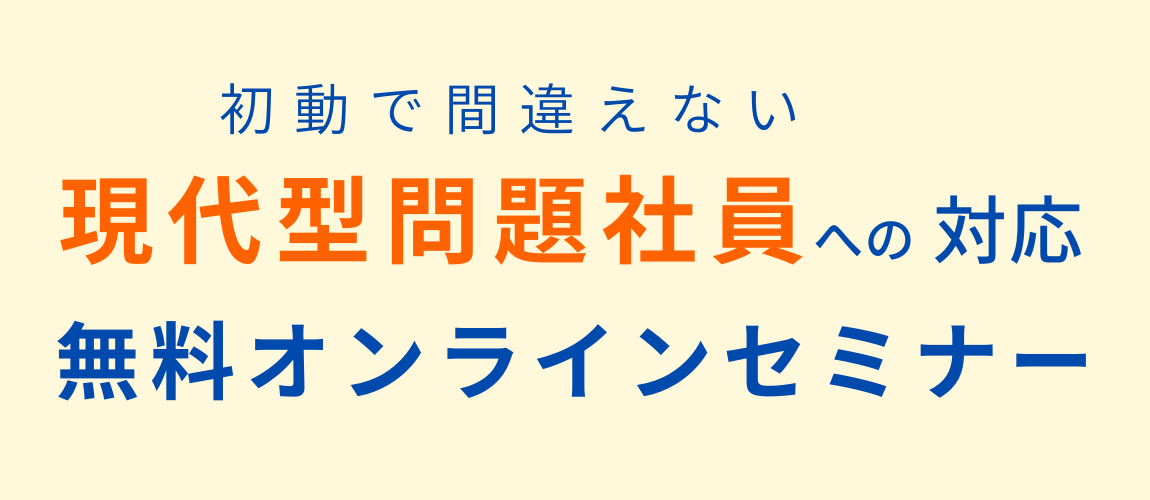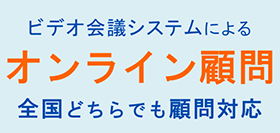今回の民法改正は、「契約解除」の実務にも影響を与える可能性があります。法律の改正に追いついていくのは大変ですが、契約解除は、どの契約においても問題となりえる事項ですので、要注意です。
今回は、契約の「解除」について取り上げます。読んでみて、今まで使ってきた契約書に不安を感じた方は、顧問弁護士に契約書のチェックなどをしてもらうとよいでしょう。
【目次】
契約解除① ~催告による解除~
民法に定められる契約の解除は2パターンありますが、まずは、「催告による解除」から見ていきます。

(催告による解除)
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
1-1 解除の前に行う「催告」とは
相手方に、契約内容についての債務不履行がみられた場合、原則としてはまず「催告」が必要になります。この催告とは、相手方に契約に基づく債務の履行を催促する行為です。
このように、解除の前に催告を必要としているのは、相手方が「うっかり忘れていた」ことが原因の不履行であれば、少し遅れてでも履行してもらった方が契約当事者にとって利益になるということが前提としてあるからです。
1-2 債務者の帰責事由の有無
従来は、相手方の債務不履行によって契約の解除をする場合には、相手方つまり債務者に帰責事由があることが要件とされていました。しかし、改正民法では、第543条後段が削除され、契約の解除そのものにおいて債務者の帰責事由は要件から外されています。
これは、民法による解除制度の趣旨を見直したことによる変化です。
改正前民法における契約の解除は「債務者に対する責任追及の手段」と位置づけられていました。これが、「債務の履行を得られなかった債権者を契約の拘束力から解放するための手段」と位置付けし直され、債務者の帰責事由という要件も、解除の要件から解除に伴う損害賠償請求のための要件へと純化されることになりました。
1-3 解除が認められない場合
基本的には、上記のように催告を行っても相手方が債務を履行しなかった場合には、契約を解除することができるということになります。
例外的に解除が認められないケースとして、「①軽微な債務不履行」や「②債務不履行が違法出ない場合」があげられます。
① 軽微な債務不履行
ひと口に債務不履行といってもその程度はさまざまです。
この点、これまでも判例では、不履行の態様が軽微であったり付随的義務のうち契約全体で見て重要度が低かったりする場合には、契約の解除を認めていませんでした。
そこで、改正民法では、「債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」(第541条ただし書き)には、解除が認められないことが明記されました。
契約解除の可否を左右する「軽微性」の判断について
㋐ 軽微性の判断時期
不履行の程度が軽微であるか否かの判断は、催告期間の経過時にてなされます。
㋑ 軽微性の判断基準
取引観念を考慮し、契約の趣旨に照らして判断されます。
「軽微」とされるのは、次の場合です。
- ⅰ 違反された義務自体が契約全体から見て軽微な場合
…付随義務のうち、重要度の低い義務の場合 - ⅱ 義務違反の態様が軽微な場合
…給付の遅れや不完全さが軽微である場合
㋒ 「軽微性」の判断実務
債務不履行による解除について争いとなった場合、軽微であることの立証責任は、債務者側にあることが明白になりました。
この点、判例による具体事例が提示されているケース以外については、どのように判断されるか計り切れない部分がありますので、今後の裁判例等で動向を注視していく必要があります。
② 相手の債務不履行が違法でない場合
契約は、双方が何らかの債務を負っていることが通常です。契約は、いわば「ギブアンドテイク」になることが多いからです。
その場合、こちらが、相手方に対して負っている債務を履行していない場合は、相手方が債務の履行を拒めることがあります。法的には、相手方が「同時履行の抗弁権」や「留置権」を有しているときです。
この場合には、こちらも履行すべき債務を履行しておかなければ、解除の効果を得ることはできません。
ところで、履行を怠っている相手方は、自身の債務履行ないしは契約の解除を避けるため、意図的にこちらの債務履行を拒絶することがあります。
こうなってしまうと、債権者としては債務の履行も受けられず解除もできない、という八方塞がりの状況に陥ってしまいます。
そこで、判例は、「債権者のなす履行を受領する意思のないことが明白な場合には、債権者は提供をしないで履行を催告し、その履行がないときには契約を解除することができる」として、債権者を救済する道を設けています。
契約解除② ~無催告解除~

次に、もうひとつの解除パターンである「催告によらない解除(無催告解除)」についても解説します。
(催告によらない解除)
第542条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- ① 債務の全部の履行が不能であるとき。
- ② 債務者がその債務の全部の履行を拒否する意思を明確に表示したとき。
- ③ 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
- ④ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達成することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
- ⑤ 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務を履行せず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
- ① 債務の一部の履行が不能であるとき。
- ② 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
2-1 催告によらない解除(無催告解除)とは
ここまで見てきたとおり、契約解除にあたっては、事前に催告をすることが原則ではあります。
しかし、催告をしても履行されないことが明白な場合にまで、催告の期間を経ることは合理的とは言えません。したがって、民法では、契約の目的を達成する履行が望めないと考えられる一定の場合には催告なしでの契約解除を認めています。これを「催告によらない解除(無催告解除)」といいます。
2-2 無催告解除の5つのパターン
改正民法第542条第1項の1号~5号では、無催告解除が認められる5つのパターンが示されています。
① 債務の履行が完全に不能な場合
例:不動産の二重譲渡が発生し、買主の片方が所有権移転登記を完了した場合
→登記できなかった買主は、当該不動産の売買契約について履行を受けることはできません。このような場合、原則は履行不能と言えるでしょう。
ただし、買戻し等によって所有権を回復することが可能な場合・仮登記の場合には履行不能とは言えないとの判例があります。
② 債務者が履行拒絶の意思を明確に表示している場合
債務の履行拒絶についての意思表示は、単に表示されているにとどまらず、「明確に」表示されていることが必要です。
よって、単に履行を数回拒んだというだけではなく、履行拒絶の意思がその後に翻されることが見込まれない程に確定的な表示であることが求められます。
③ 債務の一部が履行不能または一部履行拒絶の意思を明確に表示しており、それ以外の残存部分の履行では契約目的を達成できない場合
履行拒絶の明確さについては、②と同様になります。ただし、一部の履行拒絶では、その余の残存する部分の履行で契約の目的を達成できる場合には、その一部分に関する解除が認められるにとどまり、契約の全面解除はできません。
④ 特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約目的を達成できない場合で、債務者が履行をせずその時期を経過した場合
例:業者が中元の進物用の商品を6月中に送付するとした売買契約について、その履行がなされず7月になってしまった場合
→「中元用の品の売買」「開店のための建物明け渡し」等、特定の時期や日時を逃すと意味を成さなくなる契約については、その期限が守られなかった場合には実質的に履行不能と同様の状態となりますので、解除が認められます。
⑤ ①~④の他、債権者が催告をしても契約目的の達成が見込めないことが明らかな場合
例:売買契約において目的物に契約不適合が認められたものの、売主による追完が期待できない場合
→第5号は、契約目的達成不能による契約解除についての包括規定となっています。
注意点とポイント
① 債務不履行の帰責事由
改正前の民法においては債務者の帰責事由が解除の要件とされていましたが(第543条後段)、例によってこれが削除となりました。
したがって、無催告解除の場合でも催告による解除と同様、債務不履行に関して債務者の帰責事由は必要ありません。
② 明確な履行拒絶
これまで、解釈論上認められてきた確定的履行拒絶の場合の無催告解除について明文化されたことで、これを利用した無催告解除の主張が増加することが予想されます。
これから先覆されることのない程度の拒絶意思とはいえ、争いとなった場合にはどのような拒絶が「履行を拒絶する意思を明確に表示した」と言えるのかが問題となるのは明白であり、この点に関する判例等の動向は注視する必要があります。
契約解除の効果

契約解除に関しては、上記のほかに契約解除の効果についても変更が加えられました。
3-1 契約解除の効果
契約解除という1つの行為によって、複数の効果や権利が発生することになります。民法改正によって、解除という行為においては「契約による法的拘束からの解放」に趣旨を統一するよう、その要件から調整が行われました。そこで法律では、その他、解除から生じる「原状回復」及び「損害賠償」という関係事項について、それらが不可分なく作用することができるよう配慮されています。
(解除の効果)
第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときには、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第1項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
3-2 契約解除にともなう原状回復
契約が解除されると、解除の直接の効果として、契約上の債権・債務は初めに遡って消滅します。「初めに遡って」ですので、すでに履行がされている一部履行の債務については、金銭であるか否かを問わず目的物について、法律上の原因のない給付として返還する義務が生じます。解除の場合、この返還義務が「原状回復義務」というものです。(改正民法545条1項)。
3-3 原状回復義務の対象
改正前の民法では、金銭については受領時から利息を付して返還することを定めていましたが、金銭以外の物については受領以後の対応が定められていませんでした。
これでは、金銭以外の物の受領後に生じた果実については返還しなくてよいという誤解を生む可能性がありましたので、今回の改正によってその点が明文化されることとなりました。(第545条第3項)
3-4 注意点とポイント
① 目的物に活用した利益
また、契約によっては、不動産等の給付を受け、その不動産を利用して賃料等の収益を得ている場合が考えられます。
これについて判例は「給付を受けた金銭以外の物から生じた使用収益をも返還しなければならない」という判断をしており、家賃収入等の収益を得ていた場合には、その収益についても返還する義務を負うということになっています。
② 保証人の義務の継続
特定物の売買において、売主の債務不履行によって契約が解除された場合、原則として売主の保証人は既払代金の返済義務についても引き続き保証責任を負います。
これは、売主の債務不履行に起因して売主が買主に対し負担する可能性のある債務につき、責任を負担する趣旨で保証がなされるのが通常だからです。
保証人となる際には、この点について注意が必要です。
また、契約が解除された場合でも、債務不履行による損害賠償請求は認められます。このような保証・損害賠償については、契約締結時にもっとも注意したいポイントのひとつではないでしょうか。
新たに契約書を作成する際には、予期せぬ不利益を避けるため、顧問弁護士等によるリーガルチェックを受けられることを、おすすめします。弊所では、各種契約について契約書チェックやレビューを行っておりますので、是非、お気軽にご連絡ください。