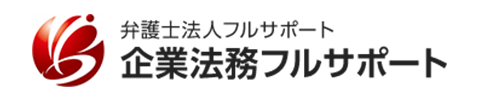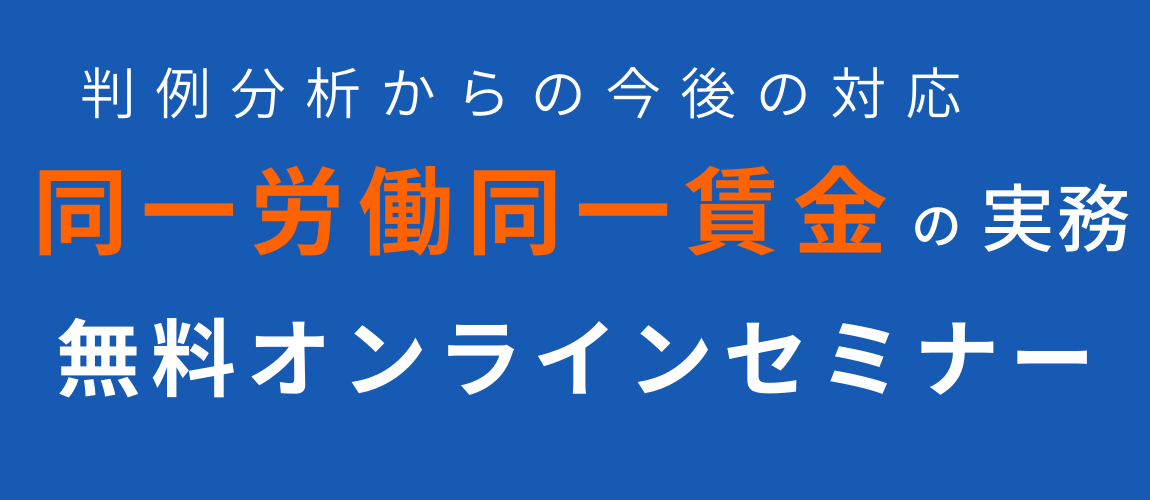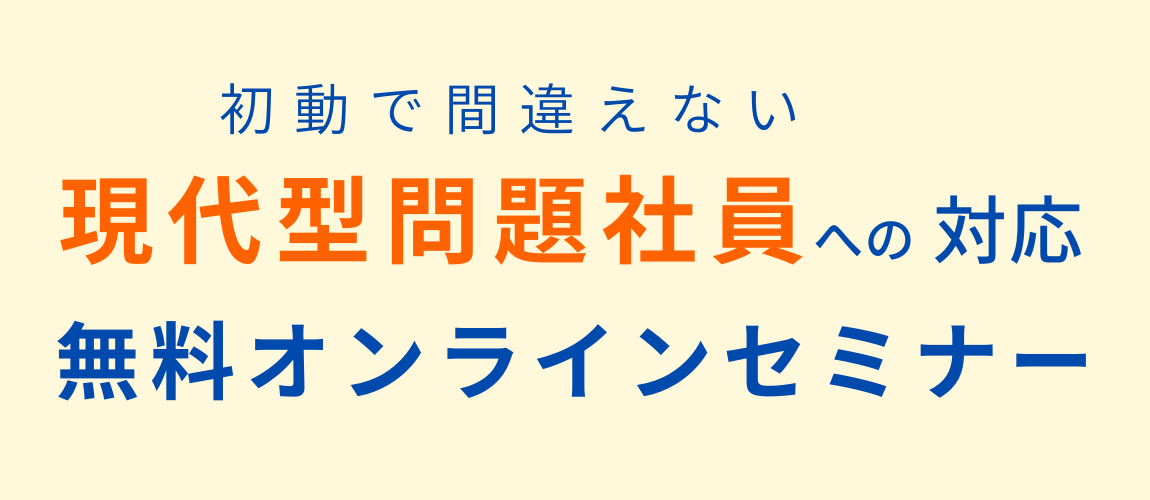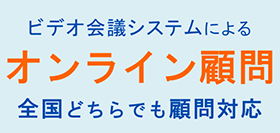当事務所では、11月28日・29日、12月3日に、「現代型問題社員への対応セミナー」を開催しました。
同セミナーでは、50人を超える参加者をお迎えすることができ、活気の溢れるセミナーとすることができました。
また、同セミナーでは、非常に考えさせられる質問をいただきました。
以下ではそのうちの幾つかの質問をピックアップして、詳しいお答えをお付けしました。
なお、次回のセミナーは、「同一労働・同一賃金」を予定しております。
来年2月19日に岐阜市で、2月20日に名古屋市で開催する予定です。
いよいよ、来年4月1日より、中小企業においても派遣社員に関しての「同一労働・同一賃金」が施行されます。法律の改正に送れないように、是非、ご参加ください。
参加申し込みについては、近日中にHPに掲載いたしますので、ご覧ください
Q 就業規則で副業を制限・禁止することはできないのか。
就業規則に制限や禁止の規定を置き、従業員と合意をすることは可能です。しかし、あとから就業規則の規定そのものの合理性が争われる可能性はあるでしょう。
副業を制限する就業規則の合理性については、仙台地方裁判所の判決(H1.2.16)が参考になります。
この事案では、従業員の副業を禁止し、その違反を解雇又は懲戒解雇事由としていたタクシー会社の就業規則について、その合理性が争点の一つとなりました。
裁判所は、まず、「余暇をいかに利用するかは原則として労働者の自由に決しうるところであり、余暇の利用には副業を営むことも含まれているということができる」と示しました。
ただし、本件ではタクシー会社という業務の性質上、事故防止のため、運転手には非番の日に十分な休養を取らせ、会社に対する労務提供を十全たらしめようとすることは当然であるとして、このような趣旨から副業を懲戒解雇事由として禁止している事には、十分な合理性があると判断しています。
したがって、この事案においては、就業規則による副業禁止には合理性があると判断されました。
しかし、この裁判例は、あくまで、タクシー会社という特殊な事情があっての例外的な判断であることに注意しなければなりません。
業務内容によっては就業時間外に十分な心身の休息をとる高い必要性が求められ、終業時間外の副業を禁止する規定が合理的と判断される場合がありますが、裁判所も示す通り、原則として労働者が余暇をどのように過ごすかは労働者の自由です。
よって、就業規則に副業を禁止する規定を置いたとしても、裁判基準ではその規定に合理性が認められないと判断され、機能しない可能性があることは認識しておかなくてはなりません。
Q 退職規定に従って希望日の1か月前に退職を申し出た社員が、最後のひと月で有給休暇の消化をしようとている。ただし、その月は賞与支給月にあたる。このように退職前の有給休暇消化期間中の従業員にも、賞与を支給する必要はあるだろうか。
就業規則や賃金規程などにおいて、賞与の支給規定がどのように定められていたかによって決まります。
一般的な賞与の支給にあたっては算定期間があるため、その期間に勤務の実績がある場合、全く支給しないという選択は難しいと言わざるをえません。
では、賞与を他の社員と比べて減額することはできるでしょうか。
①有給休暇の取得を理由とした減額
②自社での将来の活躍がないことを理由とした減額
以上の2つの方法を検討してみます。
①有給休暇の取得を理由とした減額
労働基準法136条は、有給休暇の取得を理由として、労働者に不利益な取扱いをすることを禁止しています。
この条文からは、原則として、有給休暇の取得を理由に、賞与を減額することは許されないことになりそうです。
この点、沼津交通事件において最高裁は、下記のように判断しています(H5.6.25)
①労働基準法136条は、努力義務を定めたものであり、同条に反しても、不利益取扱いが、ただちに無効になるものではない。
②不利益取扱いが、有給休暇の取得を抑制し、有給休暇利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められれば、公序に反して無効となる。
この判例は、「有給休暇を理由に、不利益取扱い(賞与を減額)することを認めた。」として、引用されることがあります。
しかし、最高裁は、②の判断を慎重に行っており、不利益取扱いが許される領域を狭く解釈していることに注意が必要です。
実際、この判例以後でも、有給休暇を理由とした不利益取扱いが認められた裁判例・判例は、極めて限定的な事例です。
したがって、有給休暇の取得を理由に減額することは、無効と判断されるおそれが高いと言えるでしょう。
②自社での将来の活躍がないことを理由とした減額
こちらは、「退職する」ということに焦点を当て、かつ、辞めるということをマイナス評価するのではなく、他の労働者が得ているプラスの評価を得られないことを理由とした減額方法です。
賞与において、このような項目が評価対象となっている場合は、他の労働者と比較して、低い賞与を支払うことも許されるでしょう。
どの程度の差をつけられるかという点については、ベネッセコーポレーション事件(東京地判H8.6.28)が参考になります。
会社Aでは、中途入社者に対する賞与支給について、退職予定者(規定には年内に退職する予定者となっていた)に対する支給額を、非退職予定者と比較して少額になる規定を置いていました。
会社Aは、この規程に従い、退職した社員に対して支給した賞与の過払い分の返還を請求したものです。
判決では、まず「退職予定者」を「少なくても、賞与支給日までに、規定の期間内で退職することが判明している者についてはこれに含まれることが明らかである」と示しています。
そして、このように退職予定者への支給額を減額することの有効性については、その減額根拠を「従業員に対する将来の活躍の期待」として「賞与額決定の要素として、従業員の将来の活躍に対する期待を加味することには一定の合理性が認められる」としています。
結果として本事案では、在社期間の短い中途入社者は将来に対する期待部分の割合が比較的多い類型の従業員であることを考慮して減額率は、「非退職予定者賞与額の2割が相当」と判断されており、実務上、非退職者と比較してこれ以上の減額は難しいと考えられます。
この裁判例は、「退職すること」を理由に、他の社員との間で、賞与の額に差を設けることを認めたものです。
しかし、他方で、就業規則や賃金規程等の賞与支給根拠規定において、賞与の趣旨が「賃金」としての性質を有する場合は、「退職すること」を理由に、賞与のうち「賃金」の部分までをも減額する行為は許されないとしていることにも注意が必要です。
「将来への期待が小さいことを名目に賃金を奪う」行為であって、労基法24条違反となると判断しています。
Q 就業規則に就業時間内の喫煙禁止を定めることはできるだろうか。
前提として就業規則に定める内容には広い裁量が認められており、どのような規定を定めるかは自由ですし、その就業規則について従業員との間で合意があれば、それは一応の義務となります。
ただし、その規定の合理性に関して後に従業員と争いになった場合には、裁判所がその判断に立ち入る形となります。この際に合理性が認められるかどうかは、その規定が実現を確保しようとする義務の重要度によります。
職務専念義務からの禁止
会社が、喫煙禁止を就業規則に定めたい理由は、幾つかあるでしょう。
そのひとつに、喫煙者のみが、就労時間に休息を取っていることへの不満が挙げられるかと思います。義務でいうならば、「職務専念義務」の違反と言えるでしょう。
しかし、ある程度の長時間の労働では、休憩時間でなくても、お茶を飲む程度の休息は許されていると考えられています。したがって、煙草を1本吸う程度の休息時間ならば、それだけで「職務専念義務」違反とは言い難いところがあります。
もっとも、経営者が本当に気にしているのは、喫煙所で談笑を始めて、なかなか帰って来ないことでしょう。この場合は、「職務専念義務」違反に当たることになりますが、就業規則で喫煙を禁止するよりは、長時間の離席を禁止することが直接的な対応となりそうです。
安全配慮義務からの禁止
別の切り口としては、従業員の健康を守る観点から、敷地内での喫煙を禁止することが挙げられます。
喫煙は現在、関連法の整備が進んでいる分野となっています。
例えば、2020年4月に施行される改正健康増進法によっては、望まない受動喫煙の防止を図るため、喫煙は喫煙専用室でのみ可能となり、それ以外の場所では禁止されることになっています。
また、労働安全衛生法においても、事業者には、受動喫煙防止のため事業場の実状に応じて適切な措置を講じることが求められています。
これを受けて、厚生労働省発行のモデル就業規則(H31.3)第10章では、その解説中に、事業場の敷地内全体を禁煙区域とすることも可能であることが示されています。このように、現在は健康維持・増進の観点から一定の範囲で喫煙を制限することに対して合理性が認められやすい時流となっています。
以上より、就業時間内の喫煙を禁止する規定には合理性が認められる可能性が高いと考えられます。まずは、「従業員の健康増進と社内の受動喫煙防止措置」を名目として定められてみてはいかがでしょうか。
ただし、現在すでに喫煙に関して就業規則内に何らかの規定がある、または何らの規定も置かれていない場合には、喫煙禁止規定を新たに定めることが就業規則の不利益変更になる場合があります。その際には、適切な手順をもって就業規則の変更を行うようにしてください。
Q 就業規則の服装規定で、スーツ着用義務を課すことはいけないのか。
繰り返しになりますが、会社が就業規則にどのような規定を定めるかは自由であり、就業規則に従業員が合意している場合にはその内容は従業員の義務となるのが原則です。
よって、服装について規定を設け、従業員がそれを遵守している場合には何ら問題ありません。
ただし、仮に当該規定の合理性が争われたときにそれが認められるかどうかは、具体的な事例に沿った判断となります。
服装規定は、ほとんどの場合がred「企業秩序維持義務」に関する規定となりますが、その合理性の判断は判例においても各事案の事情を考慮する形でまちまちとなっており、画一的な判断基準はないに等しいと言えます。
職種や、従業員が外部の人と接する機会の有無によって、服装に関して求めることができる制約の範囲は変動することになりますので、就業規則に規定を置く際には、スーツの着用を要求することに対するある程度合理的な説明を用意しておく必要があるでしょう。
実務的には入社の時点で、スーツ着用の理由を説明しておくことと、ラフな服装になり始めた場合には、素早く注意・指導をすることが重要でしょう。