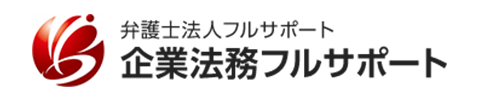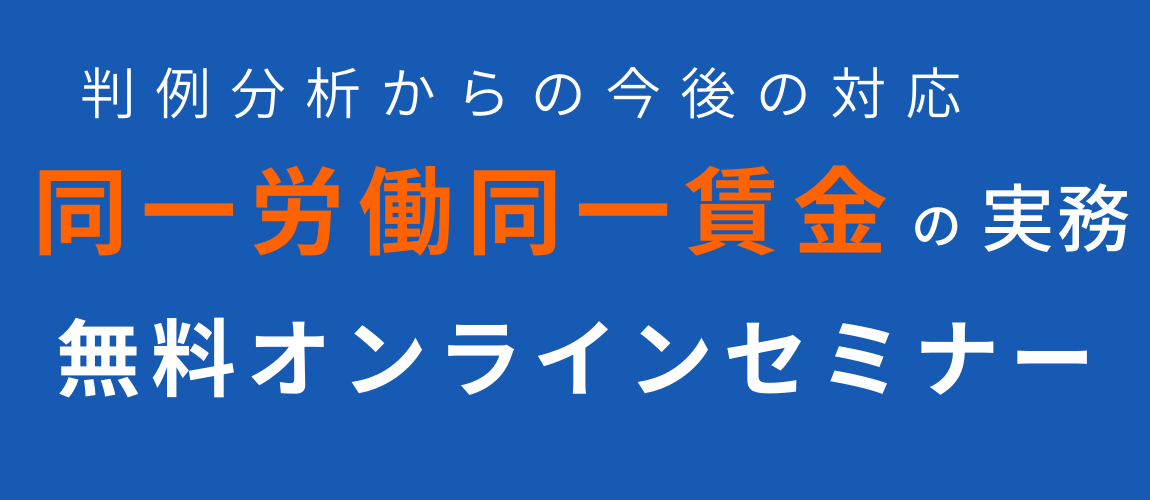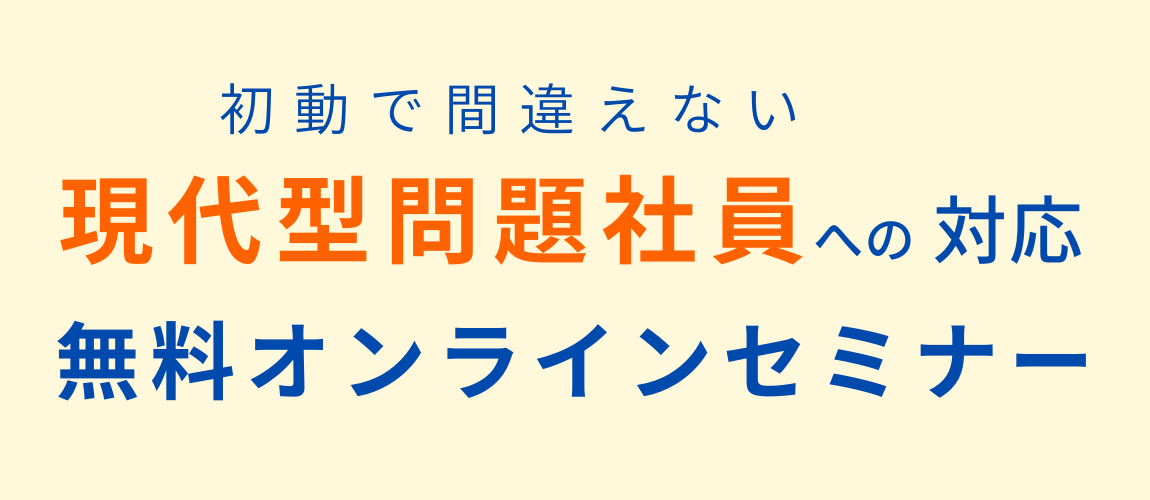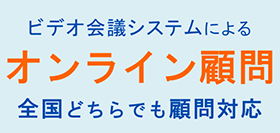事業の売上げが減った場合は、「労働条件の不利益変更」という苦渋の選択に出ざるを得ないことがあります。会社がつぶれてしまうよりは、労働条件を変更して会社と従業員を残す選択肢を採るべきときがあるからです。
当事務所の顧問弁護士となっている企業の中でも、政府や都道府県知事からの度重なる自粛要請のため、客足が激減して「コロナ不況」に陥っている企業があります。今回は、労働条件を不利益変更するときの注意ポイントについて解説します。
【目次】
労働条件の不利益変更とは
労働条件の不利益変更とは、労働条件を労働者にとってマイナスになるものに変更することです。ここでは、労働条件の不利益変更にはどのようなものがあるのか、また実際にどのような方法で変更するのかについて見ていきましょう。
労働条件の不利益変更例
労働条件の不利益変更といわれて一番に思い浮かべるのは、賃金の減額かもしれません。しかし、それ以外でも以下のようなものがあります。
- 賃金や役員報酬の一部カット
- 各種手当の減額または不支給
- 労働時間の延長
- 休日・休暇を減らす
- 福利厚生の廃止
- 固定残業代制への変更
- 年功序列型の賃金体系を成果主義型の賃金体系へ
- 休職要件・復職要件の変更
一部が不利益変更の場合
労働者にとって、一部でも不利な変更があれば、不利益変更に該当します。
つまり、労働者にとって「有利な変更」と「不利な変更」がセットになっている場合でも、「不利益変更」に該当します。
「有利な変更」の部分は、後に述べる「変更の合理性」として考慮されることになります。
不利益となる可能性の場合
成果報酬を導入した場合など、必ずしも賃金が下がるわけではない場合でも、「不利益となる可能性」があるならば、やはり「不利益変更」に該当します。
不利益変更する方法とは
労働条件の(不利益)変更には、以下の3つの手法があります。
①労働者と使用者の合意によって労働契約を変更する。
②就業規則の改定により変更する。
③労働協約の締結、改定により変更する。
以下では3つの手法について詳しく説明していきます。
①労働契約の変更

労働契約は、使用者と労働者の合意によって成立する契約です。したがって、使用者と労働者が再び合意をすることで、契約の内容を労働者にとって不利にも変更することができます。
後に述べる「就業規則の改定」による不利益変更と異なり、公序良俗(民法90条)に反しない限りは、「変更の合理性」がなかったとしても不利益変更が許される点に特徴があります。
労働者の自由意思に基づいていること
労働条件を不利益変更するときには労働者の合意が必要です。そして、その合意は労働者の自由意思に基づくものでなければなりません。会社側から不利益変更の必要性やその実施方法について十分な説明や情報提供をしたうえで、合意するかどうかを労働者自身で決めてもらうことになります。
このとき、強制的に合意させようとして「こっちはいつでもクビにできるんだ」「合意書にサインできないなら辞めてもらう」など、解雇や退職をちらつかせるような発言はNGです。また、「持ち帰って検討したい」という社員にはゆっくり検討する時間を与えて、無理矢理サインを迫ることのないようにしましょう。
また、実務上注意しなければならないのが、署名・押印をもらう前に、しっかりと不利益変更であることを説明すること」です。
この点、経営者としては、従業員に詳しい説明をしないことで、「従業員が反対意見を持つ前に合意を取ってしまいたい。」と思ってしまうことがあります。
しかし、従業員に丁寧な説明をしていなかった場合は、後に労働者から「錯誤無効(真の合意がなかったこと)」を主張されてしまうおそれがあるからです。
最高裁判決 平成28年2月19日
不利益変更に係る合意の有効性について、労働者が使用者の指揮命令に服すベき地位があることと、労働者は意思決定の起訴となる情報を集める能力に限界があることを理由に、労働者の署名・押印があるだけでは有効な合意とは言えず、署名・押印に先立つ労働者への情報提供・説明内容も考慮する必要があると判断した。
特に大幅な賃金の引き下げなどでは、説明会を開くといった対応も必要となるでしょう。
就業規則の改定
ただし、個々の労働契約の内容は、就業規則の内容より(労働者にとって)有利でなければならないとされています(労契法12条)。
したがって、合意による労働契約の不利益変更が、就業規則の内容よりも(労働者にとって)不利益になる場合は、「就業規則の改訂」も必要となります。この点を見落としやすいので注意が必要です。
その際は、以下の通常の就業規則の改定と同じ手続が必要となります。
Ⅰ 過半数労働組合又はそれがない場合は過半数代表者の意見聴取
Ⅱ 労働基準監督署への届出
合意が取れない社員に対して
もちろん、実際には賃金を減らすといった労働者に不利な労働条件変更では、全ての従業員が同意してくれるとは限りません。したがって、労働条件の変更に反対してくる従業員への対応を想定しておくことも必要です。
具体的には、次に述べる「就業規則の改訂」により、対応していくことになっていきます。
②就業規則の改定
就業規則を変更することで、不利益変更する方法があります。
就業規則の改定である以上、前述の通常の就業規則の改定手続は当然に必要となります。
しかし、ここでの問題は、「そもそも労働者の不利益となる変更が許されるか。」です。この点、労契法10条によりますと、以下の要件を満たすことにより、就業規則により労働条件の不利益変更が許されています。
㋐変更の合理性がある
㋑変更後の就業規則の周知がされている
㋐変更の合理性とは
就業規則の不利益変更において、「変更の合理性」が必要となるのは、以下の条文からです。
労働契約法第10条
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
条文によれば、以下の事情から変更の合理性を判断することになります。
「変更の合理性」の4つの判断要素
Ⓐ労働者の受ける不利益の程度
Ⓑ変更後の就業規則の内容の相当性
Ⓒ労働組合等との交渉の状況
Ⓓその他の就業規則の変更に係る事情
Ⓐ労働者の受ける不利益の程度
労働者の受ける不利益の程度とは、賃金や退職金の減額率や休日・休暇の減らされる日数、労働時間の延長時間などの度合いのことです。賃金であれば、おおむね減額率が10%より大きいときに合理性が認められない傾向にあります。これは、労働基準法第91条で、賃金の制裁について減給の幅が「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とされているためだと推測されます。
Ⓑ労働条件の変更の必要性
労働条件の不利益変更の必要性がどの程度あるか、ということも判断基準のひとつです。必要性が大きければ大きいほど、不利益変更が認められやすくなります。たとえば、今までどおりの賃金を支払っていたら会社の運転資金が枯渇するほど資金繰りがひっ迫しているときには、賃金の一部カットなどの不利益変更がしやすいでしょう。しかし、業界の将来を予測すると今のうちに資金を確保しておきたいので労働者の賃下げをするという場合は、合理性がないと判断される可能性があります。
労働条件の不利益変更の必要性がどの程度あるか、ということも判断基準のひとつです。必要性が大きければ大きいほど、不利益変更が認められやすくなります。たとえば、今までどおりの賃金を支払っていたら会社の運転資金が枯渇するほど資金繰りがひっ迫しているときには、賃金の一部カットなどの不利益変更がしやすいでしょう。しかし、業界の将来を予測すると今のうちに資金を確保しておきたいので労働者の賃下げをするという場合は、合理性がないと判断される可能性があります。
Ⓒ変更後の就業規則の内容の相当性
労働条件を不利益変更するために就業規則を変更したとき、その内容が行き過ぎたものではないか、不利益変更した内容が妥当かどうかの検討が必要です。たとえば「社員全員、一律〇万円賃金を引き下げる」といった内容は、基本給がもともと少ない社員にとって負担が大きくなるので妥当ではないと判断されることがあります。社員全員同額をカットするにしても、数年かけて段階的に賃金を引き下げていく経過措置や、賃下げ分をカバーできるような別の手当があれば、相当性が認められるかもしれません。
Ⓓ労働組合等との交渉の状況
労働組合のある会社では労働組合と、労働組合のない会社では個々の労働者と誠実に交渉をしていたかということも考慮されます。会社側が資料を用いながら十分に説明をしていたか、労働組合に何度も交渉を働きかけ不利益変更への理解を得ようとしていたかなどが判断材料になります。
実務における「変更の合理性」

以上のように、「変更の合理性」の4つの判断要素は条文上示されていますが、「1つでも欠けていれば認められない」といった厳格なものではなく、4つの判断要素(場合によってはその他の事情も)総合考慮したうえで不利益変更が妥当であるかどうかが判断されます。
しかし、実務においては、往々にして「総合考慮」は基準となりえません。明確な基準を見いだすことが非常に困難だからです。事実、「変更の合理性」については、地裁、高裁、最高裁の間で判断が分かれることも珍しくはありません。
| 事件名 | 地裁 | 高裁 | 最高裁 |
|---|---|---|---|
| 大曲市農協事件 | ○ | × | ○ |
| 第一小型ハイヤー事件 | × | × | ○ |
| 第四銀行事件 | × | ○ | ○ |
| みちのく銀行事件 第1次変更 |
○ | ○ | × |
| みちのく銀行事件 第2次変更 |
× | ○ | × |
○…変更の合理性を認めたもの
×…変更の合理性を否定したもの
裁判所の「変更の合理性」の判断
ここでは、裁判で労働条件の不利益変更が認められたケース(企業側が勝訴したもの)と認められなかったケース(企業側が敗訴したもの)をご紹介します。
これらの判例から、先ほどの4つの判断要素がどのように考慮されているか、どのような状況であれば不利益変更が認められやすいのかが見えてくるのではないでしょうか。
認められたケース①:第四銀行事件
ある銀行が、定年年齢を55歳から60歳に引き上げる際、行員の90%から成る労働組合と交渉の上、55歳以降の給与・賞与を54歳時の63~67%に引き下げるとの内容で就業規則の変更をしました。これに対し、労働組合員ではない社員が、個の変更が無効であるとして変更前の就業規則に基づいて計算した賃金と55歳以降に受け取った賃金の差額を求めて提訴した事件です。(最二小判平9・2・28 民集51巻2号705頁)
裁判所は労働者の受ける不利益は小さくないとしながらも、55歳以上の賃金見直しには高度な必要性が認められる、就業規則変更は全行員の約90%から成る労働組合との交渉・合意を経て行われたので合理的と一応推測できるとの理由で、会社が行った就業規則の不利益変更には合理性があると判断しました。
認められたケース②:ノイズ研究所事件
原告Xらが勤める会社で、競争力強化のため年功序列型から成果主義に給与制度が変更されました。その結果、Xらの給与が月額約7万2,000~3万4,000円の減給となったため、減額分の支払いを求めて会社を提訴した事件です。(東京高判平18・6・22労判920号5頁)
裁判所は、給与の総額を減らさずより合理的な配分にしようとしたこと、労働組合との団体交渉を通じて円滑に変更しようとしていたこと、経過措置として不利益を緩和する措置が取られていたことなどを評価。そのため、制度変更には高度な必要性があるとの判断を下し、原告らの訴えを認めた第一審判決を取り消し、請求を棄却しました。
認められなかったケース①:ニチネン事件
ある会社Yの営業部員Xが、会社側から営業成績不振を理由に賃金を半額にすると通告されました。さらに会社側は「解雇予告を払えばいつでもXを解雇できるから」と解雇をにおわせ、退職するか賃金半減を受け入れるかを一両日中に決めるようXに迫った事件です。(東京地判平30・2・28労経速2348号12頁)
裁判所は、減額期間を定めずに賃金を半減することにより原告が著しい不利益を強いられること、十分な熟慮期間を与えられることなく原告が減額を受け入れたのは、原告の自由意思に基づくと認められないとして、賃金減額は無効であると判断しました。
認められなかったケース②:北海道国際空港事件
ある航空会社が、経営不振のために課長以上の賃金を平成13年7月から20%、同年12月からさらに15%減額しました。社長付担当部長が7月18日にすでに働いた分には遡及できないと抗議したものの、同月25日から支払われた減額賃金をだまって受け取り続けます。しかし、翌14年8月に退社後、賃金減額が無効であるとして航空会社を提訴したのがこの事件です。(最一小判平成15・12・18労判866号14頁)
この事件では、1審・2審では減額された賃金を異議なく受け取っていたことから原告の請求は棄却されましたが、最高裁では同月1日から24日分の賃金については明確な意思表示があったとは言えず、賃金規程の規定振りから同月25日から31日分も従前の賃金額になるとして、会社側に対し同年7月分の減額分と遅延損害金の支払いを命じました。
㋑就業規則の変更を周知したこと
労働組合または個々の労働者と労働条件の不利益変更について合意が得られたら、就業規則の変更が必要です。労働基準監督署に変更の届出をした後は、社内に就業規則の変更をした旨を周知しなければなりません。誰でも立ち入れるフロアに掲示する、イントラネットにアップするなど、全社員がいつでも見られるところにおくことが必要です。
労働者に変更の周知がなされていなければ、労働基準法違反で30万円以下の罰金に処せられることもありますので、くれぐれもご注意ください。
③労働協約の締結・改訂
労働組合のある会社では、「労働協約」の内容を変更することでも不利益変更することができます。
労働協約は原則として、労働協約を締結した労働組合の組合員にしか及びませんが、「変更の合理性」が不要という特徴をもちます。
なお、1つの事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上を組織する労働組合と労働協約を締結すると、非組合員にも効力が及ぶとされています(一般的拘束力)。
「③労働協約」は、有利不利を問わず「①労働契約」・「②就業規則」よりも優先されることに注意が必要です。
すなわち、「①労働契約」や「②就業規則」を改定したとしても、過去に定めた「③労働協約」と反する場合は、「①労働契約」と「②就業規則」は効力を生じないことがあります。まずは、「③労働協約」の有無から確認するべきです。
労働条件を不利益変更するリスク
労働条件を不利益変更すると、会社は一時的には助かるかもしれません。しかし、不利益変更にはリスクもありますので、そのことを頭に入れたうえで検討することが重要です。
士気の低下を招く
労働条件を悪いほうに変更されてやる気になる労働者はほとんどいないでしょう。不利益変更が一時的なものであれば「今だけだ」と考え、まだがまんできるかもしれません。しかし、自分にとって不利になる労働条件がずっと続くようであれば、だんだん社内全体の士気が低下して、労働者の反発を招いたり離職率が高くなったりする可能性もあります。その結果、かえって業績が下がることも懸念されるでしょう。
訴訟を起こされるおそれがある
労働者の士気の低下によって、訴訟を起こされるリスクも無視できません。過去には、会社の都合で賃金を減額された労働者が、後になって給与の差額を請求する訴訟を起こしている例がいくつも見られます。訴訟になれば、弁護士費用など余計な出費が発生する上に、敗訴すれば訴額に加え遅延損害金まで支払わなければならないこともありえるでしょう。
ブランドイメージが低下する
労働者から訴訟を起こされると、大手企業であればマスコミに取り上げられる可能性がありますし、中小企業であっても近隣住民の間でそのうわさが拡がる可能性もあります。労働条件の不利益変更が原因で訴訟を起こされていることが世間に知られれば、その企業に対するブランドイメージが低下し、顧客離れによる売上減につながることもあるでしょう。また、「あの会社はブラック企業だ」とのレッテルを貼られることで求人募集をしても優秀な人材が集まらない懸念もあります。
まとめ
労働条件の不利益変更は避けたほうが無難です。しかし、今回の「コロナ禍」のように外部の環境が大きく変わった場合などは、不利益変更せざるを得ないこともあります。経営者としては事業を守る責任もあるからです。
その場合は、労働者に対して丁寧に説明し、法に則った手順で実施すべきでしょう。
正しい手続で、誠意をもって公平な説明をすれば、労働者も合意をしてくれることが多いというのが、企業側の弁護士としての実感です。不利益変更が合理的かどうか、就業規則や労働協約はどのように変更すべきかわからないときは、遠慮なく弁護士に相談されることをおすすめします。