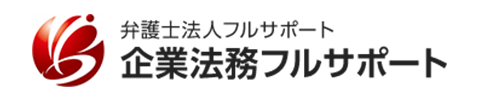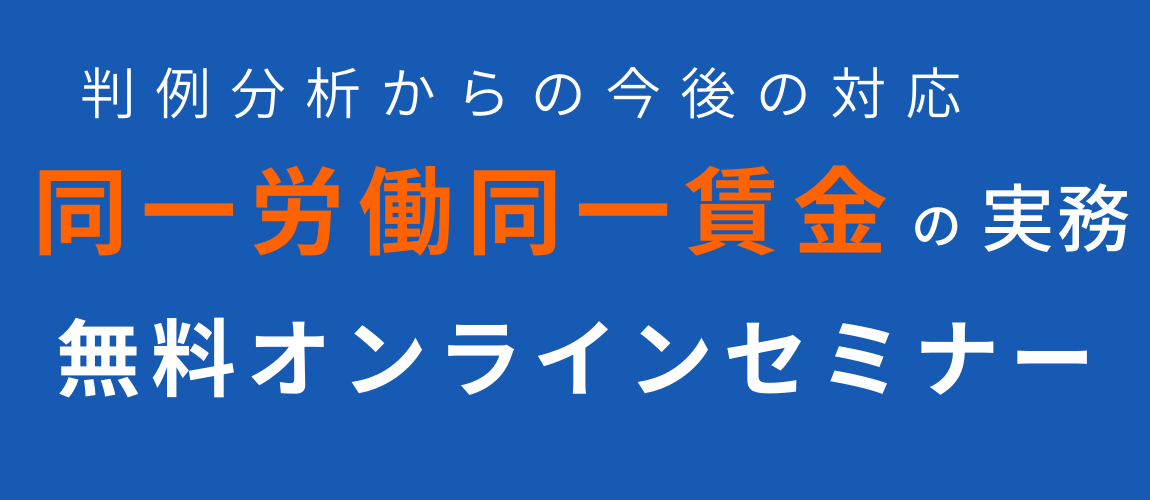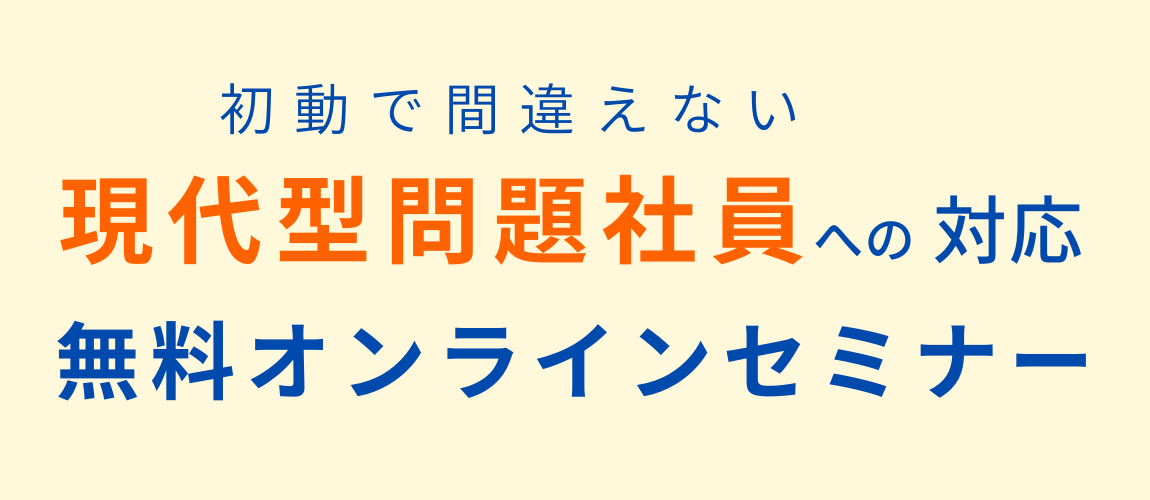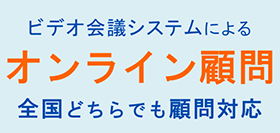しっかりと作られた契約書は、「証拠」として非常に強い力を持っています。
それは、当事者間に「どのような合意があったか」の証拠となる力です。
契約書は、両当事者が署名・押印しますから、両当事者がどんな合意をしていたかを、強く証明することができるのです。
当事務所は、契約書の作成・チェックにAIプログラムを利用するなど、非常に力をいれています。
顧問先に対して、「問題(紛争)が生じたときに負けないよう」に、さらに一歩進んで、「問題が生じないよう」なルールブック(契約書)を作るようにしています。
本稿では、「いかにして合意内容を契約書に残すか。」という点にフォーカスをあてます。
契約書は勝利に導く証拠
当事務所は、多くの企業法務の御相談をお受けしていますが、何かトラブルが起きたとき、
「当社は間違っていないから、あとは弁護士がすぐに終わらせてくれるだろう。」
と考えて、ご相談にいらっしゃる方がいます。
しかし、弁護士は、依頼者の主張だけを聞いて、すぐに動き出すことはありません。まずは、証拠を拝見して、裁判を行った場合に勝訴できる確率を予測します。
なぜならば、相手と交渉するとしても、勝訴できる確率が高ければ有利に交渉を進められますが、そうでない場合には妥協案を探す必要があるからです。
そして、勝訴できる確率を上げるものは「証拠」です。裁判になった場合、主張の土台となるものは証拠だからです。
したがいまして、万が一、何かトラブルが発生してしまった際、有利な解決をするために大切なのは、トラブル発生後の対応ではなく「日常的に適切な証拠化を行うこと」なのです。そこで、証拠化の効果的な方法の一つとして挙げられるのが「契約書の作成」です。
そこで、以下では企業の顧問弁護士としての視点から、契約書の重要性と作成のポイントを解説していきます。
契約とは
そもそも、契約とはなんでしょうか。一言で言えば約束と言えそうですが、正式には「複数当事者の意思表示が合致することにより成立する法律行為」です。
企業の中で発生する契約には、例えば、商品の販売をする「売買契約」、従業員を雇用する「雇用契約」、商品生産の受発注を行う「請負契約」などが挙げられ、大小さまざまな契約が日々成立しています。
このような契約ですが、実はそのほとんどが契約書という書面を取り交わさなくても当事者同士の合意のみで有効に成立します。では、なぜ弁護士は口を揃えて「契約書は重要」と言うのでしょうか。
契約書が役に立つのはいつか
なぜ契約書が必要なのか。その唯一の答えが「万一紛争が発生した際に自社を有利な結果へと導く証拠となるから」です。
仮想事例
例えば、A社とB社の間で次のような合意ができていたとします。
- A社はB社の商品Xを100万円で買う。
- 商品Xは受注生産なのでB社はA社から代金100万円の支払いを受けてからXの製造を開始する。
- そして、代金支払い日の3カ月後に納品を完了する
しかし、A社は100万円を支払ってからひと月後に、「B社から商品Xの納品が無いためこれは債務不履行である」として契約の解除と商品Xの代金100万円の返還を迫ってきました。
B社としては、Aの注文を受けて商品の製造を開始してしまっているでしょうから、代金を返還してしまっては損失であり、当然そのような合意と異なる主張を受け入れて契約を解除するわけには行かず「納品日は3カ月後とする契約であるためB社に債務不履行はなく契約の解除は認められない」と主張するでしょう。
では、この事案が裁判になった場合には何が争点となるのでしょうか。
…それは「商品Xの納品日を代金支払日の3か月後とする旨の合意をしていた」という事実があったかどうかです。
裁判において事実の認定は、証拠によって行われます。
残念ながら「確かに3か月後の納品で合意したんです」とどれだけ熱弁しても裁判官には認めてもらえません。
また、当事者のうちどちらかが紙きれに残していたメモなどが出されたとしても、後からいくらでも都合の良いように作成できるものであれば信用度は低いと言わざるを得ません。
ここで、「契約締結時に合意していたことを明確に示すことができる証拠」となるのは、まさに契約書なのです。
契約書に書くべきこと
契約書の有無によって、裁判での勝敗が大きく左右されることはお分かりいただけたと思います。そこで次に重要なのが、契約書に何を書くかということです。
裁判による事実認定と言いますと、小難しく聞こえるかもしれませんが、認定する内容はいたって単純なものになります。
例えば、次のようなことです。
「代金はいくらだったか」
「契約の目的物は何だったか」
「いつまでに果たされるべき契約であったのか」
何も難しい記述はないはずです。
難しくないはずのことが難しくなってしまうのは、残しておきたい事実へのイメージが足りないからです。
証拠の観点から契約書を作成する場合、契約書には最低限、当事者の互いの債務の内容を具体的かつ明確に記載するようにしましょう。つまり「いつ」「誰が」「誰に対して」「何を」「どうする」債務があるのかを記載しておかなくてはならないということです。
契約書のファーストステップ

それでは、契約書において記載すべき最低限の事項について、よくある例と適切な記載方法を見ていきます。
①当事者を特定する条項
「〇〇株式会社△△△△(個人名)」これって法人?個人?
「〇〇株式会社△△△△」、よく目にする表記のように感じます。
しかし、実はこの表記では「〇〇株式会社」と「△△△△(個人名)」、どちらが当事者なのか非常に不明瞭と言わざるを得ません。
一般的に契約書においては賠償能力の観点からも法人を当事者とするべきですので、個人名を付したい場合には「〇〇株式会社代表取締役△△△△」として、法人の代表者として法人の意思を示していることを明らかにする必要があります。
多数当事者の契約書はより慎重に
当事者が多数である場合には、「誰が」「誰に対して」負う債務なのかをより明確に記載する必要があります。二者間契約書と同じ感覚で作成された契約書では、まま、漠然と「債務を負う」と書かれているものが存在します。
当事者が多数の場合には、誰が誰に対して履行すべき債務なのかをより明確に記さなくては、思わぬ損害賠償を請求されることになりかねません。
「この契約書の効力は第三者にも及ぶ」の落とし穴
「この契約書の効力は第三者にも及ぶ」…自社の契約書に見当たる場合は要注意です。
契約書の当事者としてその契約書の効力を及ぼすためには、必ず署名押印が必要です。当人の与り知らないところで「第三者」として契約書に巻き込んでいても、その効力は到底及びません。
よって、効力を及ぼしたい「第三者」は、契約当事者に入れて、署名押印の対象としなければなりません。
②目的物を特定する条項
この請負、完成?未完成?
請負契約という形の契約を締結する機会は何かと多いのではないでしょうか。
請負契約は、工事やソフトウェア開発などで多く見られる契約形態ですが、仕事の完成を目的物として、その対価が支払われる契約です。そのため、契約当事者間の「完成」にズレが生じると、それが直接的に支払いの拒否に繋がってしまいます。
さらに、紛争になることが多いケースとして、一度完成とした仕事について、修正と称して追加の仕事を行うことになった場合の料金の支払いが挙げられます。発注者は「諸段階の完成が契約の目的を達していなかったのだから、修正は最初の契約内容に含まれる。追加料金は発生しない。」と言いますし、請負人は「完成後に追加で仕事をしたのだから、追加料金を支払え。」と言うでしょう。
こうならないためには、仕事の完成レベルについて具体的に細かく特定しておくことが必要です。請負契約では通常、設計図や仕様書が複数回にわたって作成されますので、目的物として「〇年〇月〇日付設計書・仕様書のとおり」と都度更新していく必要があります。
「秘密」だと思わなかった
様々な情報がビジネスにおいて重要な役割を果たすようになってきた近頃は、多くの企業間取引において秘密保持契約/条項が採用されていますが、「秘密とは、本契約に基づき開示される甲又は乙の営業上又は技術上その他業務上一切の情報をいう」という条項、自社の契約書に見当たりませんか?
上記の問題点は、秘密として流通を制約する範囲が明確に限定されていないことです。「営業上又は技術上、業務上」では秘密を特定するには不十分と言わざるを得ず、契約の相手方が「営業上又は技術上、業務上」の情報ではないと考えて情報を流通させてしまった場合、自社が負けてしまう可能性は高くなります。
よって、秘密保持契約においては、目的物とする情報の内容をなるべく具体的に明記します。例えば「顧客情報」「〇〇製品に関するデータ」などと特定し、さらに、契約書の段階で書ききれない部分を補完するために「書面・口頭のいかんを問わず秘密である旨明示した情報」と開示方法によっても特定していくのです。
③履行方法を特定する条項
目的物の引渡し場所はどこ?
多くの契約が、商品やサービスの「引渡し」とその目的物に対する「支払い」で成り立っているでしょう。この、引渡しについて、その履行場所は契約に定めなければ民法の定める通りになることをご存じでしょうか。
民法の定めは次のようになっています。
特定物売買 … 債権発生の時にその物が存在した場所(民法484条前段)
種類物売買 … 債権者現在の営業所(ない場合は住所)(民法484条後段)
よって、特定物に関しては契約によって買主の所に持ってくるように定めておかなければ「頼んでいる物が一向に届かないがどうなっているのか?」という状況になりかねないのです。
支払条項はとにかく細部まで
支払条項に定めることは「支払額」「支払い方法」「支払日」となります。
支払額に関しては、税込か税別かを必ず明記しましょう。次に支払方法については、一括なのか分割なのか、現金持参なのか銀行振込なのか等、希望の方法を定めておく必要があります。多くの場合、銀行振込を利用するでしょうが、その場合には振込手数料をどちらが負担するかについても定めておきましょう。
支払条項はとにかく細部まで
契約において相手方に債務の履行を請求するには、弁済期が到来していること、つまり「債務を履行しなければならない日が来ていること」が必要です。まだ約束の日が訪れていないのに「早くやれ」というのはあまりに不合理なのはお分かりいただけるでしょう。
よって、万が一の場合には確実に履行請求を行うためにも、引渡し・支払い共に、弁済期は明確に「〇〇年〇月〇日限り」というように具体的な日付を指定しておくべきでしょう。また、定期的な複数回に渡って履行が行われる場合にも、「毎月〇日限り」というように規定するのが望ましいと考えられます。
唯一無二の契約書で万全の備えを
この記事では、証拠としての観点から、契約書の重要性と最低限の記載事項について簡単に説明しました。しかし、実際に企業法務で求められる契約書は「最低限」ではなく「最大限」です。
契約書は「証拠」としての力のみならず、「ルールブック」としての力もあります。
ルールブックとしての力を発揮させるためには、「危険負担」「契約不適合(瑕疵担保)責任」「損害賠償」「管轄」「解除」など、契約形態や目的物に合わせて様々な条項を定める必要があります。そして、これらの条項はただ定めれば良いのではなく、具体的な取引を分析した上で、万が一の事態において自社を守ることができるよう、様々な可能性を考え抜いて定められなければなりません。
契約書法務において何が重要か、何が有効か、弁護士はその答えに最も近い存在です。契約書の作成・リーガルチェックは、弁護士に任せてみてはいかがでしょうか。
当事務所は、契約書・就業規則等の作成・リーガルチェックから日々の労務問題まで幅広く企業法務に対応しております。契約書に特化した顧問プランもご用意しております。まずはお気軽にご相談ください。