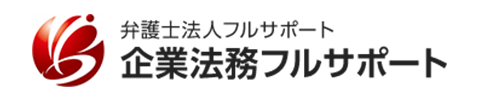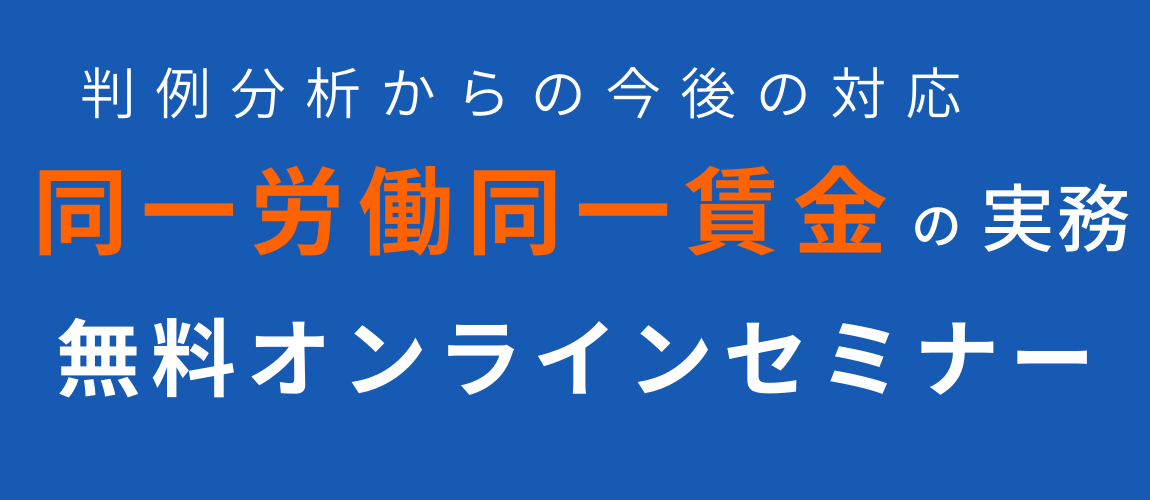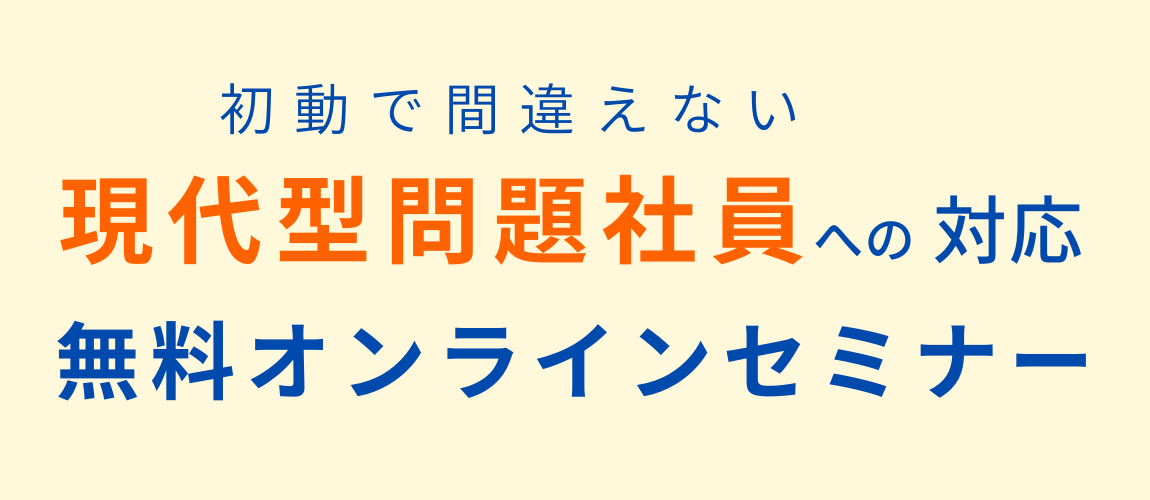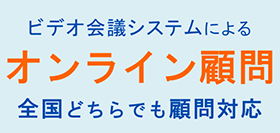前回は、2020年4月1日より施行された改正民法により,損害賠償の制度が変わりました。これに伴い,契約書も変更を余儀なくされています。
損害賠償に関する条項が契約書に入っていると,つい身構えるという方は必見です。
「考えたくない状態」は,「紛争となりやすい状態」ですから,しっかりおさえておきましょう。
1.損害賠償
1 – 1:債務不履行による損害賠償請求
損害賠償とは、相手方の債務不履行ないし不法行為により,何らかの損害が生じた場合に,相手方に請求できるものです。企業取引の場面では、契約によって生じた債務の不履行によって損害を受けたときに多く利用されます。
例えば,ある売買契約が成立したとき,買主には「売主に代金を支払う」という債務,売主には「買主に商品を引き渡す」という債務が生じます。そこで,買主が代金を支払ったにも関わらず,売主が商品を引き渡さなかった場合,売主は債務を履行していないことになります。
この売主の状態を「債務不履行」といいます。また,売主の債務不履行によって商品が手に入れることができなかった買主は,売主に対して「損害賠償請求」をすることができます。
1 – 2:損害賠償の免責
ただし,損害賠償には,免責事由,つまり債務不履行を引き起こしても賠償責任を負わない場合が存在します。
実務上,免責が認められるのは「履行不能を含む債務不履行全般において,債務者の責めに帰することができない事由によるものである場合」で,そのような免責事由の主張立証は,債務者がしなければならないとされています。
改正民法では,旧民法ではあいまいであった文言を修正し,上記実務上の取扱いを忠実に条文として表現しています。
改正民法第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
また,新法では、帰責事由の有無についての判断枠組みも明記されました。
新法415条ただし書きには,「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき」とあります。
なお、この改正は,従来の実務運用を踏まえて枠組みを明確化したにとどまり,この規定によって実務の在り方が変わることは想定されていません。したがって,この点は旧民法と同様に任意規定という扱いになりますので,契約によって書き換えることはできます。
例えば,契約の特約において「特定の瑕疵について無過失の賠償責任を負う」という規定が設けられている場合には,わざわざ取引上の社会通年等に照らして免責事由の有無が判断されることはなく,当該特約が適用され損害賠償責任が生じるということです。
1 – 3: 填補賠償
従来から,債務不履行があった場合,債権者は,一定の要件の下で債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができました。これを一般的に「填補賠償」と言います。
旧法の下でも,填補賠償の請求を行うことは可能であると解されていましたが,明確に規定としては設けられていませんでした。そこで,改正民法では,一般的な解釈も参考にしつつ,填補賠償請求の要件とともに当該請求が可能であることを明確にする規定が新設されています。
改正民法第415条第2項(債務不履行による損害賠償)
前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において,債権者は,次に掲げるときは,債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
- 一.債務の履行が不能であるとき
- 二.債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
- 三.債務が契約によって生じたものである場合において,その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき
填補賠償の要件
改正民法415条第2項各号には,填補賠償の要件が3つ挙げられており,債務不履行の態様がそのいずれかに該当する場合には填補賠償の請求が可能ということになります。
①債務の履行不能
最も典型的な場合にあたります。契約で定めた債務が履行不能になってしまった場合に,本来の債務の履行に代えて損害賠償請求を認めるものです。
②債務の履行拒絶
履行拒絶というのは,債務者が,一切履行する意思がないことを明確に表示している場合を指すとされています。つまり,履行自体は可能であり履行不能ではないが,履行の意思がなく,実質的には履行不能とみなせる状況です。判例でも,履行不能に準ずる場合として損害賠償が認められています。
しかし,明確な拒絶とは言っても,どの程度で明確と言えるのかが問題となります。この点,単に履行を拒んだというだけでは足りず,履行拒絶の意思がその後に覆されることが見込まれない程に確定的なものであることあ必要である,とされていますが,実務上この規定がどのくらいの実効性を持つことになるかは,今後注目されるところです。
③契約解除又は債務不履行による解除権の発生
契約が解除された場合は比較的分かりやすい要件になります。
また,解除の意思表示がされていなくても法律上解除権が発生しているときも,要件に該当します。これには例えば,履行遅滞後に債権者が履行の催促をしたにも関わらず,相当期間を経過してもなお,債務者が履行をしなかったような場合が想定されています。
2.履行遅滞中/受領遅滞中の履行不能に関する損害賠償責任
債務者もしくは債権者の責任で,契約内容の履行が完了していない間に,何らかの事由により履行不能となってしまった場合には,どちらがその責任を負うことになるのでしょうか。

2 – 1:“履行“遅滞中の履行不能
旧法下では,以下のような場合に誰が損害賠償責任を負うかの明文規定はありませんでした。
- ①債務者の帰責事由に「よる」履行遅滞中に,
- ②債務者の責任ではない理由で履行不能となった場合
しかし,実務上,このような場合は,「債務者」が履行不能による損害賠償の責任を負う,という判例法理が成立していました。
そこで,改正民法では,履行遅滞中の履行不能と帰責事由についての規定が新設されました。
改正民法第413条の2(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)
債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは,その履行の不能は,債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
この状況に陥った場合の立証責任については,債務者が「履行不能は自身の責めに帰すべからざる」ことについての立証責任を負担するとされています。
2 – 2: “受領”遅滞中の履行不能
一方、債権者の責任で受領遅滞となっている間に,当事者双に責任のない事由で履行不能に陥ってしまった場合にまで,債務者に責任を負わせるのは相当ではないでしょう。
そこで、受領遅滞の場合には第413条の2第2項において,「受領遅滞中に当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行不能となったときは,その履行の不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」とされました。
これにより,債務者は,受領遅滞中の自身の責任でない履行不能については損害賠償責任を負わないこととなります。
3.損害賠償の合理的な範囲とは

契約がスムーズに運ばず,何らかの不都合が生じた時,「どこまでの損害について,賠償するべきか」という問題は,しばしば争われるポイントです。
「風が吹けば桶屋が儲かる」ではありませんが,ときに,債務不履行が,どんどんと損害を呼び寄せることもあるからです。
債権者としては,その契約が履行されなかったことで生じるその先の損害を含めて,できる限り広範囲に賠償責任を設定したいと考えるでしょう。
一方、債務者としては「そんなことまで知らないよ」という債権者都合の損害については,賠償責任を負いたくないはずです。
このような,損害賠償の「範囲」については,改正民法第416条が規定していますので,詳しく見て行きます。
改正民法第416条(損害賠償の範囲)
- 債務の不履行に対する損害賠償の請求は,これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
- 特別の事情によって生じた損害であっても,当事者がその事情を予見すべきであったときは,債権者は,その賠償を請求することができる。
3 – 1: 「通常生ずべき損害(通常損害)」の賠償が基本
改正民法第416条第1項は,債務不履行に対する損害賠償請求は「通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的」としています。
これを「通常損害」といい,そのような債務不履行があれば通常発生するであろうと考えられる損害を指します。この「通常損害」に対する賠償が基本となっています。
3 – 2: 「特別の事情によって生じた損害」の賠償は例外的
一方、同条第2項には,特別の事情によって生じた損害「特別損害」が規定されています。この特別損害に対する賠償が認められるのは,「特別の事情に対する予見すべきであったとき」となります。
旧法では,「当事者がその事情を予見し、または予見することができたとき」債務者に賠償責任があるとされていました。
この点,改正民法では「予見すべきであったとき」と表現が改められています。
旧法の下より裁判実務においては,当事者が特別の事情を実際に予見していたかではなく,当事者がその事情を予見すべきであったと言えるか否かという規範的な評価によって,その事情によって生じた損害が賠償の範囲に含まれるかを判断していました。
今回の改定によって,予見に関して規範的な評価が問題とされるということが,条文上明確になりました。
特別の事情に対する予見が問題となるのは例えば…
事例: 売主A,買主Bの不動産売買において,Aが,当該不動産において引渡債務を履行しませんでした。しかし,その時既にBは当該不動産について転売契約を結んでおり,これに高額な違約金条項が付されていたとして,BがAにこの違約金の損害賠償を請求したケース
この時,Bには「特別な事情」として「高額な違約金条項による違約金の発生」があります。しかし,この高額な違約金条項の存在をAが予見することができたかどうかを議論しても,なかなか結論が出ないでしょう。Aの能力によっても異なる結論になってしまうからです。
裁判例や改正法のように,「予見すべきであったか」という規範的な評価によるならば,Aの個人的な能力は,ある程度,捨象することができます。
また,賠償の範囲は「予見すべきであったと客観的に評価される事情によって生じた損害」となり,結論としても妥当なものに落ち着くことができます。
なお,判例(大判大正7年8月27日)では,債務者にとって履行期に予見可能であった事情が賠償の可否の判断の基礎になるとされています。
上記の例でいえば,Bから,契約締結前に転売契約のことを聞かされていた場合には違約金の少なくとも一部は予見すべきであった事情によって生じた損害として,Aは賠償責任を負うことになるかもしれません。
4.法定利率変更の影響

4 – 1: 法定利率とは
期限に遅れる債務不履行において発生する賠償金を,遅延損害金と言います。
遅延損害金は,一定の利率によって算定されますが,①その具体的な利率は契約内に定めるか,②定めていない場合は法が定める利率に従うことになります。
この,法が定める利率のことを「法定利率」といい,民法改正によって変更された項目の一つです。
4 – 2: 法定利率と運用の変更
旧民法においては,法定利率は年5%であり,商行為によって生じた債務に関しては商法の規定に基づいて年6%となっていました。
しかし,この利率が,市場金利との乖離が著しく実情にそぐわないという問題を受けて以下のように変更されました。
(第4項・5項省略)
また,民法改正とともに,商法の法定利率を6%とする規定も削除されました。これにより,商行為によって生じた債務についても,契約で特段の定めがない場合には民法の法定利率に従うこととなります。
4 – 3: 3年ごとに利率が変動する「変動利率」
この改正によって,法定利率は従来のように固定ではなくなり,3年を1クールとする変動利率制度へと変更されました。
2020年4月1日時点での法定利率を年3%とし、その後は3年ごとに法務省令の定めに基づき算出される基準に基づいて利率が見直されます。つまり、市場金利の動向を法定利率にも随時反映させていくという方法です。
4 – 4: 法定利率が適用される基準時は?
変動利率制の下で,契約において特段利率の定めをしていない場合に遅延損害金が発生すると問題になるのが,「どの時点の法定利率を適用するか」ということです。
そこで、改正民法419条は「給付を目的とする債務の不履行については,その損害賠償の額は,債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める」としています。よって,施行日後に契約ではなく,債務者が遅滞の責任を負った場合,改正法の法定利率が適用されることになります。
4 – 5: 3%を超える利率は無効?
ただし、改正民法第419条第1項ただし書きには,次のように定められています。
「約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による」
つまり,この法定利率はあくまでも任意規定です。よって,契約内で法定利率を上回る遅延損害金利率を定めている場合は,契約上の利率が適用されます。そのため、遅延損害金の利率については,契約内で「固定利率」を定めておくべきでしょう。
仮に定めていなかった場合は,年3%の利率による遅延損害金しか請求できないことに加え,履行遅滞のタイミングによって利率が変動してしまうため,実際に請求できる金額が,契約時点で概算される金額を大きく下回ってしまう可能性もあります。
4 – 6: 利率変更の影響:番外編 “交通事故の賠償金は上がる”
ここまでに述べたとおり,事前に契約できる場合には,当事者の合意によって時には法定利率とは異なる利率を定めておくことができます。しかし,交通事故は偶発的に発生するものなので,事前に利率の合意をすることはできず,法定利率が用いられることになります。
ここで,法定利率になるなら賠償金額は下がるのか,というと,実は逆です。交通事故の賠償金のうち後遺障害等がついた場合に認められる「逸失利益」については「増額」することになります。
逸失利益は「事故に遭わなければ将来得ていたはずの利益」を仮定して賠償する,というものですので,将来稼ぐ予定だった賃金を賠償金として一括で支払ってもらうイメージです。よって,支払われる際には「中間利息控除」といって,多少の減額がなされ,いわゆる現在価値での支払いがなされます。この割引率に,事故時の法定利率が利用されます。
よって,この場合には利率が低い方が控除される額は少なく,賠償金の額は高くなります。例えば,年に100万円を10年間分請求する権利を得た場合,利率が5%だと約772万,一方3%だと約853万円の賠償額となり,約81万円も増額することになります。
民法は,ビジネスにおける契約等の企業法務的にはもちろんのこと,私たちの私生活にも深く関わっている法律です。
当事務所は顧問先様に対し,ビジネス上の法務サポートに加えて「EAP(従業員支援プログラム)」のサービスを提供させていただいております。
同サービスでは,従業員の私生活における法的問題,交通事故・離婚・相続等について相談をお受けすることができます。ご興味がございましたら,ぜひ一度,当事務所までお問合せください。